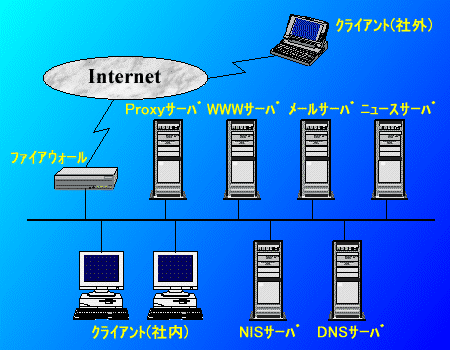
イントラネットはインターネット技術を用途別に使い分けるのが大きな特徴です。
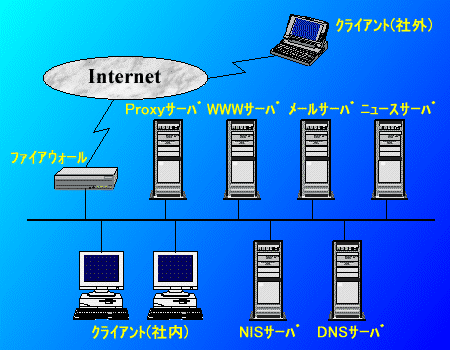
イントラネットで何を行うかによって使う技術は変わってきますが、それらの技術はイントラネットにおいて次のような用途で使われます。
| 技術 | 用途 |
|---|---|
| WWW | 主に情報発信型の情報共有に向く。 分散型(例えばセクション毎)の情報の管理ができる。 情報と情報の間にリンクを張ることで、情報の関連付けをすることができる。(表面的にはオブジェクト指向的データベース)。 マルチメディアのコンテンツ(動画,音声等)を扱うことが出来るが、リアルタイムを要求されるデータの再生は基本的に不可能。 情報の参照は可能であるが、情報の書き込みにはかなり工夫が必要である。 |
| いわゆる電子メールである。 個人と個人の情報交換に向くが、ML(Mailing List)を用いることで、電子会議モドキのことは可能であるが、全社レベルでの情報交換・共有には向かない。 |
|
| NetNews | いわゆる掲示板・電子会議室と呼ばれるもの。 WWWと違い文字ベースの情報の共有しかできないが、情報の書き込みが容易にできる。そのため、Q&Aなどの利用においては、情報が情報を産み相乗的な情報の共有が可能である。 一般にNetNewsは非リアルタイム型の電子会議であるが、工夫次第でリアルタイム型の電子会議が可能となる。また、社外のニュースグループを社内に配送してもらうことで、情報の幅が拡がり、特にエンジニアには有用な情報が多く蓄積されている。 |
| DNS | マシン名とIPアドレスの対応表を集中的に管理できるため、クライアント毎にその対応表を持つ必要がなく、メンテナンスが容易となる。 InternetがNetworkのNetworkと呼ばれるのも、このDNSという仕組みがあるからである。 |
| NIS | 複数のサーバのユーザ定義情報(パスワードなど)を一元管理することが可能。 社内で統一したユーザアカウント管理ができ、保守工数の削減やパスワードの更新が容易になるため、セキュリティを強化できる。 入を防ぐ。 |
| Proxy | クライアントとサーバの間に位置するもので、サーバからのサービスをProxyサーバで中継(代行処理)し、クライアントへサービスを提供する。 キャシング機能により、ネットワーク負荷を軽減させることができる。 WWWやNetNewsのProxyが有効であるが、特にNetNewsにおいてはサーバに跨がったニュースグループをマージして、ユーザに提供することにより、ユーザにあたかも1つのNetNewsサーバへアクセスしているように見せることができる。 |
| FireWall | LANのみでイントラネットを構築している場合は、この機能は必要ない。 LAN-WAN接続を行うときに必要となるもので、社外からの企業内への不法侵入を防ぐ。 |
| WAIS | 全文検索サービスで、NetNewsなどのテキスト情報をキーワードで検索することが可能。 WWWとNetNewsをWAISで連携させることで、WWWとNetNewsの短所を補うことができ、双方向の情報共有を可能とさせる。 |
| FTP | バイナリデータ(アーカイブなど)の共有を行うことができる。 ファイル名でしか目的のファイルを検索できないので、RDBなどと連携させて使うとそれなりに使える。 |
| 暗号化 | 電子メールで比較的良く使われる。 社内のみでの情報交換なら特に暗号化の必要はないが、社外のインターネット経由で電子メールを交換する場合、途中で盗み見される可能性があるため、公開鍵/秘密鍵を用いて本文を暗号化することで企業秘密の漏洩を防ぐことができる。 |
| 認証 | 情報のアクセス制御では、認証により確認されたユーザ名を用いる。 インターネット技術はオープン性を売りにしているので、全く逆のセキュリティについては甘い面がある。 しかし、この面も工夫次第である程度解消される。 |